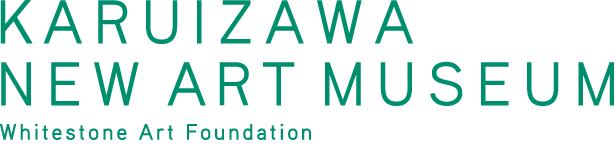「虹」の周辺―靉嘔について 本江邦夫(美術史家)
「評価」というのは別言すれば、ある人物、事項にたいする決まり切った記述であり、形容である。しかし、そこには無数の削除、無視、変換(しかも意図的な)が介在している。靉嘔の場合なら「虹の芸術家」―これ自体は間違いでも何でもない。しかし―ここが重要なのだが―だからといって、戦後日本の文化的混沌が生み出した、この稀代の芸術家の本質、すなわち徹底的な前衛性のすべてが「虹」に尽くされるわけではない。いつ、なぜ、いかにして「虹」が生じたのか―この点を究めないかぎり、靉嘔について本当の意味で語ったことにはならない。そのためには、私たちは靉嘔の原点まで下りていかねばならないのだが、そのとき否応なしに気づくことがある。その名声、親近性にもかかわらず、この芸術家にはいまだ正当な評価が無い、もっともっと評価されてしかるべきだという意外な事実だ。
靉嘔は1931年茨城県に生まれた(本名は飯島孝雄)。教育大学に在学中に当時の前衛の最先端、読売アンデパンダンに出品し、真正なモダニスト瑛九の主宰する、自由で上下関係のないデモクラート美術家協会にも加入した彼が、中学校教師の安定した人生を投げ捨てて58年―大変な苦労をして―前衛の新しい中心地ニューヨークへと向かったのは、いわば当然の成り行きだった。
当時のニューヨークは抽象表現主義の真っ最中で、最初はその影響下に制作し、それなりの手ごたえもあったが、自分の言いたいことを「どんな方法を使っても言いたい」彼がそんなことで納得するわけがなかった。それに目下流行の絵画は、河に飛び込んで水しぶきを上げる人の気分を、本体を無視し「水しぶきをキャンバスにかけて」情緒的に表現するだけのもので、「客観的拠りどころの証明には不十分」だった。過去を全否定した上での、芸術の揺るがしがたい、あえて言うなら具体的な根拠が靉嘔には必要だった。彼の非凡はそれを自らの感覚、すなわち「視・聴・触・味・嗅の五感覚に加えて予測のテレパシーの第六感」のみに求めたところにある。こうして、周囲の「物質」が「六感覚にあたえるものを見きわめ、確かめていくこと」が彼の「任務」となった。後に彼は、それを「既製の物品(オブジェクト)から霊感を引き出す」と言っている。靉嘔のそうした営為がいかに先端的であったかは、リトアニア出身の先天的な組織者ジョージ・マチューナスの主宰する国際的な前衛運動「フルクサス」との関わりの重要さからもよく分かるだろう。
特筆すべきは、世界の物質性への急速な傾斜と並行して生じた「ジョン・ケージの《四分三十三秒》」体験である。ピアノを前にしてピアノを弾かないピアニストの情景を思い浮かべた靉嘔の身体に「すさまじい衝撃が走った」。彼は言う。「今でもこの瞬間、今のぼくが生まれたのだと思っている」と。ここで問題は、空虚さの充実の隠喩的提示とも言うべき「弾かないピアニスト」(中島敦の物語る、弓を忘れた名人をふと思う)と、靉嘔的な「物質」の感覚的な具体性がどのように交わるかということだ。一方で「物質」、一方で「空虚」ないし「無」。禅問答を拒否したとき、両者はどのように関係しあうかということだ。正解はどこにあるか分からない。しかし、確実に言えることが一つだけある。「虹」に目が眩むのではなく、靉嘔という存在を虚心に受け止めると、その根底には深遠な問いかけがあることが直観されるということだ。
一見したところ異質の二つのものがあるとき、反応は二つに分かれる。一つは無関係。もう一つは、底の方では繋がっているという予測であり、これこそが靉嘔の立場であろう。これを端的に示すことで大いに評判を呼んだのが、1966年の第33回ヴェネチア・ビエンナーレにおける、《虹の環境No.3-ベニスの触覚の部屋》だ。空間全体を支配する「虹」の視覚と、壁に取り付けられた65個の、中に何が入っているか分からないフィンガー・ボックス(穴から指を入れる)の触覚の対立的共存である。特筆すべきは、「新聞等の表紙を飾った回数だけに基づくと、靉嘔の《触覚の部屋》はもっとも話題となり、議論の的となった作品だった」(M.R. Sullivan, Sculptural Materiality in the Age of Conceptualism , Routledge, 2016)ということだ。特に箱は中の仕掛けに驚かされる人が続出することが問題となり―ニューヨーク・タイムズ紙(7月4日付)によれば―途中から看視が付けられることになった。
靉嘔が虹にこだわったのは、人工的な線に対して、色彩に自然=宇宙の根源、無限性を見たからである。この立場は、純粋な単色絵画で名高いイヴ・クラインのそれと不思議に似通っている。彼は言う。「線は無限を貫いて旅するが、色彩はそれ自体が無限である。色彩を通じて私は宇宙との全面的な一致を体験する。その時私は真に自由である」(1958年)と。
根源的な立場は事物にも発揮される。身辺のものをキャンバスに取り付けた、それ自体は革新的な自作に、あるとき靉嘔は「自由でなく硬直した死の様相」を直観する。そして、これではだめだと事物を吊るすことへと発想を展開する。芸術的認識の、これは見事な飛翔である。吊るされたさまざまな既製品は、まさに「判断停止」の権化としてそこに「在る」。そして事物とは何か、人間とは何か、二つまとめて人の暮らすこの世界=社会とは何か、まさに根源的な問いかけを誘発してやまないのである。靉嘔のコンセプトのこうした奥深さはもっともっと注目されてしかるべきであろう。