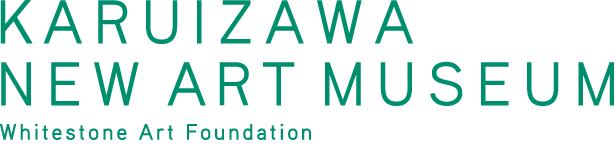GURIPOPOの作品には度々、白黒の動物が登場する。ポップなカラーリングやキャラ化されたようなフォルムの動物たちに入り混じるように登場する、これらの白黒の動物たちはひときわ異彩を放つ。というか異臭をも放つ。
動物がモチーフとなった絵画やイラスト、グッズはこの世の中に数多に存在し、写実的に描かれるものも多い。しかし“写実的な動物”を描くことに何の意味があるのか分からない。リアルな動物が好きなのであれば、写真で十分である。ましてや今の世の中、本物を見ることも可能である。「動物をリアルに描くことができるんだ」という作家の写生技術のひけらかしなのではないかとも思えてしまう。そんなのは非常に残念である。
大切なのは写実画から垣間見える作家の個性である。そもそもが写実画であるのだから、写実的に描くことができれば完成なのであるとも言える。しかし、それでは面白くない。作家が絵を描き、表現するのであれば、描く人の個性をしっかりと込め、自己をアピールしてもらいたいものである。作家のこだわりが込められた写実画こそが“個性的な写実画”として写真にも勝るリアリティと、芸術作品としての本分を得ることができる。
GURIPOPOの描く“写実的な動物”に込められた個性とは、言うなれば生き物特有の“生”のリアリティである。GURIPOPOの動物による表現は、動物が「生物(いきもの)=生物(なまもの)」であるということを思い出させ、視覚からとらえられた情報が、想像の条件反射により嗅覚までも刺激する。「動物の“生臭さ”を表現したい」と自ら述べてくれたGURIPOPO作品に良く登場する「クマ」と「ヒツジ」、「ペンギン」といった3種類の動物が特に強烈であり、作家のこだわりが強く反映されていると感じられた。この3種類の動物を言い換えるのであれば「野生」、「家畜」、「海の生き物」である。それぞれ異なるフィールドに生きるからこその、異なる臭いを想像させられる。
まずは「クマ」の臭いである。日本にも生息している大型の野生動物であるが、クマの臭いを直接嗅いだことのある人は少ないと思う。しかし、毛皮を有する哺乳類の持つ独特な“獣臭さ”は誰しもが想像することができるのではないだろうか。また、山や森を住処とし、果実や木の実、魚などを食べることなどから、“クマの臭い=自然の臭い” とイメージさせられることもありえる。
GURIPOPOの描くクマの胴体は黒やこげ茶色に塗られている。厚く重なるクマの毛皮を絵の具の濃淡で描き分け、口の周りに露出した皮膚の部分は対照的に白い。呼吸をし、食物や水分を摂取する器官である口周りは、みずみずしい皮膚感とわずかばかりの光沢を表現し、“生臭さ”を強調する。一匹一匹描かれる「クマ」の絵は、体の大きさや構図等によってそれぞれ異なる表情をみせてくれる。しかし、「クマ」の絵を通して私たちは野生の臭い、すなわち“自然界そのものの臭い”までも連想させられる。
“野生”を象徴するかのような「クマ」とは異なるのが、「ヒツジ」である。いわゆる“家畜”であり、“野生”とは反対の位置に存在する動物であると言える。牧場の柵の中で生まれ、その生涯を終えていく家畜からは“野生”の臭いを感じることはできない。しかしヒツジをはじめ、ウシやブタといった生産動物特有の臭いは確かにある。寝て食べて寝て食べてをひたすら繰りかえす生産動物の独特の生活臭は、出産から死までを人間にコントロールされているという悲壮感と相まって不思議な臭いを醸し出す。また、大草原で戯れ、嬉しそうに草を食むヒツジはさぞかし爽快な香りだろう。
GURIPOPOの「ヒツジ」の羊毛に注目したい。これは同じく同作家の「アルパカ」シリーズにも言えることではあるが、絵の具に含ませた水分を操り、滲ませぼかすことで羊毛特有の柔らかさや空気を含むかのような膨らみ、立体的な陰影さえもを巧みに表現する。
最後に「ペンギン」である。先に述べた2種類の動物とは異なり、“海に生きる生物”であるペンギンは、陸上生物とは異なり圧倒的に水分量が多い。要するに“湿り気” である。また、ペンギンの主食であろう生魚は何よりも“生臭い”という言葉が似合い、それを食するペンギン自体も“生臭さ”を醸し出す。鳥類であるペンギンの羽が水で濡れる様や、黒羽が濡れることで光るツヤは哺乳類の毛皮とは異なる様相を持つと言えるが、そこからは“海の臭い”を感じることさえできそうである。
これまで述べてきた3種類の生き物の他にも「ウサギ」や「ネコ」、「バク」や「ハリネズミ」と様々な動物が登場する。これらの動物の多くは白と黒の2色を基調として描かれる。確固たる存在感の黒と、透明感のある透き通るかのような白の間に位置する無限の無彩色表現は、陰影や立体感、柔軟さ、複雑に絡み合う密集度を表現し、水分量の調節により時に荒々しく、時に柔らかくなる。ぼかしや滲みによる技法と、白を茶色やグレーで汚していくかのような面的な着色により、みずみずしい絵肌となり“生”のリアリティを生み出させる。この“生”のリアリティこそがGURIPOPOの言う、“生臭さ”であり、一般的な“写実的な動物”ではないGURIPOPOの個性が含まれた独自のリアリティであると言える。言い換えるのであればGURIPOPOの動物作品が魅せるアイデンティティである。
主任学芸員:鈴木